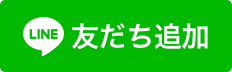お知らせNEWS & TOPICS
- HOME
- お知らせ
健康情報
ミルモくんの健康情報~頭痛について~
今回は、多くの方が日常的に経験したことのある『頭痛』について、様々な症状と原因等を説明いたします。
頭痛の種類
① 一次性頭痛
『片頭痛』や、主にストレスがきっかけとなる『緊張性頭痛』、慢性的な痛みを繰り返す『群発頭痛』等のことを言います。
命には別条のない頭痛ではありますが、仕事が手につかないなど、日常生活に支障が出る可能性もあります。
② 二次性頭痛
脳や身体に異常があって発生する頭痛のことで、今までに味わったことが無いような痛みや手足の麻痺を伴うなど、重篤な症状(クモ膜下出血等)があります。
頭痛の原因
片頭痛が発生する原因には、ストレスや寝不足、天候や気圧の変化、二日酔いなど様々です。
また、頭、首、肩の筋肉の緊張によって血行が悪くなることが原因にもなります。
一方、今までに経験したことがない頭痛、急激に起こった頭痛、意識障害を伴う頭痛、原因不明の高熱、嘔気、嘔吐を伴う頭痛、手足の麻痺、物が二重に見える、言語障害等の神経症状を伴う頭痛の場合は、クモ膜下出血や脳出血などの重篤な疾患の可能性も否定できません。
頭痛の治療
一次性頭痛では鎮痛剤等の薬物治療が主となりますが、症状によって使用する薬も異なります。
二次性頭痛では、原因となる病気の治療(手術等)が主となり、病気が根治するまでは薬物治療も継続して行なわれます。
最後に
頭痛は日常的に良くある症状ですが、『軽い頭痛だから』と放置していたら重篤な疾患が潜んでいたという可能性もあります。
全身のチェックのために定期健診は必ず受診し、痛みが続く場合や、いつもとは違う症状等があるときは、早めにかかりつけ医を受診しましょう。

【おすすめ健康レシピ】
※PDFファイルです。
(資料提供:JA熊本厚生連)
お知らせ
6月1日は「牛乳の日」、6月は「牛乳月間」です。

6月1日は牛乳の日(World Milk Day 世界牛乳の日)
「World Milk Day(世界牛乳の日)」は、FAO(国際連合食糧農業機関)にて2001年に提唱された「牛乳の記念日」です。
日本でもそれにあわせて6月1日を「牛乳の日」としています。
「牛乳の日」からスタートする6月は「牛乳月間」
6月は食育月間でもあり『牛乳と食、健康』を考えるいい機会にしたいですね。
キャンペーン情報
\『春の新商品』プレゼントキャンペーン 開催!/

本日より、らくのうマザーズ公式Instagram(@rakunoh_mothers)をフォロー及び対象投稿に「いいね」をしていただいた方の中から、抽選で30名様にいちごババロア・LLホワイトピーチが当たるキャンペーンを開催します!
【いちごババロア】
フレッシュないちごピューレを使用し、香り豊かでやさしい甘さ🍓
阿蘇山麓生乳と自家製純生クリームを使用しています👀
【ホワイトピーチ】
国産白桃果汁×ヨーグルト!🍑
ヨーグルトは牛乳由来の素材と2種類の厳選した乳酸菌です🥛
常温保存OKでストックにも便利!
応募締切は2025年5月30日(金)です。みなさまのご参加お待ちしております✨
らくのうマザーズLINE・Instagram公式アカウントにて情報発信しておりますので、是非お友だち追加・フォローをよろしくお願いいたします。
健康情報
ミルモくんの健康情報~ストレス性の不眠~
ストレス性の不眠について…
日常生活においてストレスは切っても切れないもので、人間関係や仕事などからストレスを感じ、非常につらい『不眠』に陥ることもあります。
不眠とは、睡眠の質や睡眠の量が著しく低下し、日中に不調(眠気など)を引き起こす状態のことで、主な原因としてはストレスが考えられ、その他にも生活習慣の乱れや心の不調などがあり、厚生労働省の「国民健康・栄養調査」(2023年データ)によると、日本では成人の25%は慢性的な不眠に悩まされていると報告が上がっています。
不眠が慢性化すると生活習慣病、心臓・脳血管の病気、うつ病などの精神的な病気を発症する可能性が高まり健康状態が悪化するため、不眠の予防が重要です。
不眠を予防するには?
不眠を予防するには、心(こころ)と体(からだ)の健康を保ち、生活の質を高めることが必要です。
具体的には、「趣味に没頭する」「適度な運動で心地よい汗を流す」などで、ストレスを解消し生活リズムを整えましょう。
また、寝る前の携帯電話の使用を控え睡眠の質を高めることも効果的です。
なお、ブルーライト(パソコン、スマートフォンなどから発する青白い光のこと)は、体内時計に強い影響を与えるため、遅くても寝る30分前までには照明を落としリラックスして過ごすことをお勧めします。
ストレス解消にむけて!
以下に紹介する対処法を行い、適度なストレス解消を行いましょう。
① 深呼吸をする。②ストレッチで体をほぐす。③ぬるま湯で半身浴をする。④お気に入りの音楽を聴く。⑤アロマなどで好きな香りを楽しむ。⑥森や海などの自然に触れる。
なお、現代はパソコンやスマートフォンの普及でより多くの人々がストレスを感じやすくなったと思われます。
特に強いストレスを感じた人は、夜も眠れず『不眠』になる場合もありますので、一人で悩まずストレスが限界に達する前に専門家や周りの人に相談してください。

【おすすめ健康レシピ】
※PDFファイルです。
(資料提供:JA熊本厚生連)
商品情報
2025年春 新商品のご紹介
らくのうマザーズでは、4月1日から新商品を発売します。
ぜひ、ご賞味ください。


ホワイトピーチ ヨーグルト風味 250ml
白桃果汁とヨーグルトをミックスした、やさしい味わいの果汁入飲料です。
ジューシーな白桃果汁にヨーグルトをブレンドし、華やかな味わいに仕上げました。
(国産白桃果汁使用)

らくのうブレンドコーヒー 1000ml
【パッケージリニューアル】
レトロで可愛らしい復刻デザインにリニューアルしました。
コクのあるミルクとビターなコーヒーをブレンドした、マイルドな味わいです。
コーヒーは、ミルクとの相性がよい香り豊かな深煎り豆を厳選しました。